最近ニュースやSNSでよく見かける「こども誰でも通園制度」。
名前だけ聞くと「いつでも、誰でも預けられるのかな?」と思ってしまいますよね。
でも、実際には自治体によって対象や時間の制限があり、
「思っていたのと違った」と感じる人も少なくありません。
ちなみにこの制度は、まだ始まったばかり。
現時点では全国の一部自治体・園で試験的に導入されている段階で、
2025年度に制度として整備され、2026年度から全国的な展開を目指しています。
つまり、これから少しずつ利用できる地域や園が増えていく見込みです。
僕自身も最初は“誰でも”という言葉に惹かれて調べてみたのですが、
調べていくうちに、制度の背景や現場での実態が見えてきました。
この記事では、パパ目線で感じた「こども誰でも通園制度」のリアルを、
できるだけわかりやすくまとめていきます。
🟧 第1章:こども誰でも通園制度とは?

「こども誰でも通園制度」は、保育園や認定こども園などに通っていない家庭の子どもでも、
短時間だけ園で過ごすことができるようにする新しい制度です。
国が進めている子育て支援モデル事業のひとつで、
2024年度から一部の自治体で先行して始まり、順次全国に広がりつつあります。
この制度の目的は、
「保護者の負担を軽くしながら、子どもが地域や社会とつながるきっかけをつくる」こと。
育児の孤立を防ぎ、親のリフレッシュや在宅ワーク中の支援にも役立つと期待されています。
ただし、“誰でも”という名前の通りに「いつでも・どこでも預けられる」という意味ではなく、
利用できる時間や対象、実施施設には制限があります。
🟨 第2章:勘違いしやすいポイント
「誰でも通園できる」――
名前だけ聞くと、保育園に通っていない家庭ならすぐ使えそうに思えますが、
実際にはそう簡単ではありません。
まず、実施している自治体が限られています。
同じ市町村でも、一部の園だけが対象というケースも多く、
「近くの園では実施していない」ということもあります。
さらに、利用時間は月10時間前後など、短時間利用が前提。
「毎週決まった時間に通う」ような使い方は難しく、
予約や抽選になる場合もあります。
つまり、制度としては“誰でも”だけれど、
実際には「条件を満たした家庭が、限られた時間をうまく使う」もの。
このギャップを知らないと、利用を検討したときに「思っていたのと違う」と感じるかもしれません。
🟩 第3章:対象・条件・利用までの流れ
利用できるのは、原則として保育所などに在籍していない家庭の子どもです。
対象年齢は自治体によって異なりますが、仙台市の場合は
生後6か月〜満3歳未満の子どもが対象です。
利用の目安
- 利用時間:月10時間以内(1回あたり2〜3時間など)
- 利用頻度:週1回程度の短時間利用が中心
- 利用料金:1時間あたり数百円〜(自治体・園によって異なる)
申し込みの流れ(例)
- 市の子育て支援課や公式サイトで実施園を確認
- 利用希望の園に連絡して、事前登録または面談
- 利用日を予約(空き状況によって変動)
- 当日、子どもを連れて登園(持ち物や連絡帳などを確認)
このように、基本的には一時預かり制度に近い形で利用します。
ただし園によって、受け入れ日・時間・定員・持ち物が異なるため、
事前に園へ確認しておくことが大切です。
🟩 第4章:仙台市の実施例(実際に調べてみた)

「こども誰でも通園制度」は全国的にモデル事業として始まっていますが、
仙台市でもすでに令和7年度(2025年度)から本格的に取り組みが進められています。
仙台市では、「乳児等通園支援事業」という名称で制度を運用しており、
対象は 市内在住の生後6か月〜満3歳未満の子ども で、
保育所や認定こども園などに在籍していない家庭が利用できます。
利用できる時間はおおむね 月10時間以内。
「ちょっと子どもを預けたい」「在宅ワーク中に集中したい」
といった短時間ニーズに応える形で設計されています。
🏫 仙台市で実施されている主な園(2025年度時点)
仙台市の公式サイトによると、2025年度は以下のような保育所・こども園で
「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」が実施されています。
- 青葉こども園(青葉区宮町)
- 原町すいせんこども園(宮城野区清水沼)
- あそびまショーこども園(若林区伊在)
- 鹿野なないろ保育園(太白区鹿野)
- やかまし村こども園(泉区野村)
このように、仙台市内の各区で少なくとも1か所以上が実施されており、
市内全域で制度が広がりつつあることがわかります。
このほかにも複数の園が実施事業所として選定されていますので、
利用を検討する場合は最新情報を仙台市公式サイトで確認するのがおすすめです。
👉 仙台市「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」公式ページ
💬 パパ目線のひとこと
名前だけ聞くと「どの園でも・いつでも預けられるのかな?」と思いがちですが、
実際には利用時間・回数・施設数に限りがあります。
それでも、在宅勤務や家事で一時的に時間を確保したいときなどには、
頼りになる制度のひとつです。
🟦 第5章:パパ目線で見たメリット・デメリット
「こども誰でも通園制度」は、名前のインパクトが大きいぶん、
実際に利用してみると「助かる部分」と「ちょっと使いづらい部分」が両方見えてきます。
ここでは、パパ目線で感じるメリット・デメリットを整理してみます。
✅ メリット
① 短時間でも預けられる安心感
在宅ワークやリモート会議のときなど、「数時間だけ見てもらえる」とすごく助かります。
フルタイムの保育とは違い、柔軟な使い方ができるのが魅力。
急な用事やリフレッシュにも利用できる点は大きいです。
② 子どもが“園の生活”を体験できる
家庭保育だけだと、どうしても他の子との関わりが少なくなりがち。
短時間でも園で遊んだり、先生と関わることで集団生活への慣れにもつながります。
「保育園ってどんな感じ?」を知る“おためし”にもなりますね。
③ 保護者のリフレッシュにもなる
預けている間に家の片付けや買い物を済ませたり、
ほんの少しの一人時間を持つことで気持ちがリセットできます。
育児中は「何もしていない時間」が意外と大事だったりします。
⚠️ デメリット
① 利用できる枠が限られている
「誰でも」とはいえ、実際に利用できる園や時間は限られた数。
人気の園はすぐに予約が埋まることもあります。
希望日に預けられない場合もあるので、早めの申込みと柔軟な予定調整が必要です。
② 月10時間以内という上限
制度上、月10時間までと決められています。
「週1回2〜3時間程度」だと、使い切るのもあっという間。
継続的に利用したい場合は、他の一時預かりやファミサポとの併用も検討を。
③ 自治体・園ごとにルールが違う
仙台市のようにモデル実施している地域もあれば、まだ始まっていない自治体もあります。
また、同じ市内でも園によって申し込み方法や時間帯、持ち物などが異なるため、
最初は少し戸惑うかもしれません。
④ 子どもが慣れるまで時間がかかることも
保育園では通常「慣らし保育」の期間がありますが、
この制度は短時間・一時的な利用が中心。
そのため、初めて預ける場合は子どもがずっと泣いてしまうことも。
先生方も慣れていますが、親としては心配になりますよね。
最初の数回は短時間から始めて、子どもの様子を見ながら慣らすのが安心です。
🟨 第6章:まとめ|誤解せず上手に使おう

「こども誰でも通園制度」は、“誰でも・いつでも預けられる”という印象を持ちやすいですが、
実際には自治体や園によって条件や定員が異なり、
利用できる時間にも制限があります。
それでも、在宅ワーク中のパパやママ、
家事・育児を一手に担っている家庭にとって、
「数時間だけでも子どもを安心して預けられる」というのは大きな支えです。
この制度は、保育園に入園していない家庭が
社会とのつながりを持つきっかけにもなります。
短時間とはいえ、園の先生やほかの子どもたちと関わることで、
親子どちらにも“少しだけ心が軽くなる時間”が生まれるはずです。
💡 上手に使うためのポイント
- 利用前に、自治体サイトや園に直接確認して条件を把握しておく
- 初めての利用では、子どもの様子を短時間から慣らす
- 制度を「預ける手段」だけでなく、家庭を支える仕組みのひとつとして捉える
これから制度が全国的に広がることで、
「子育て家庭が少しでも自分らしく暮らせる社会」に近づいていくはずです。
パパとしても、“無理をしすぎない育児”を支えてくれる制度のひとつとして、
前向きに活用していきたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
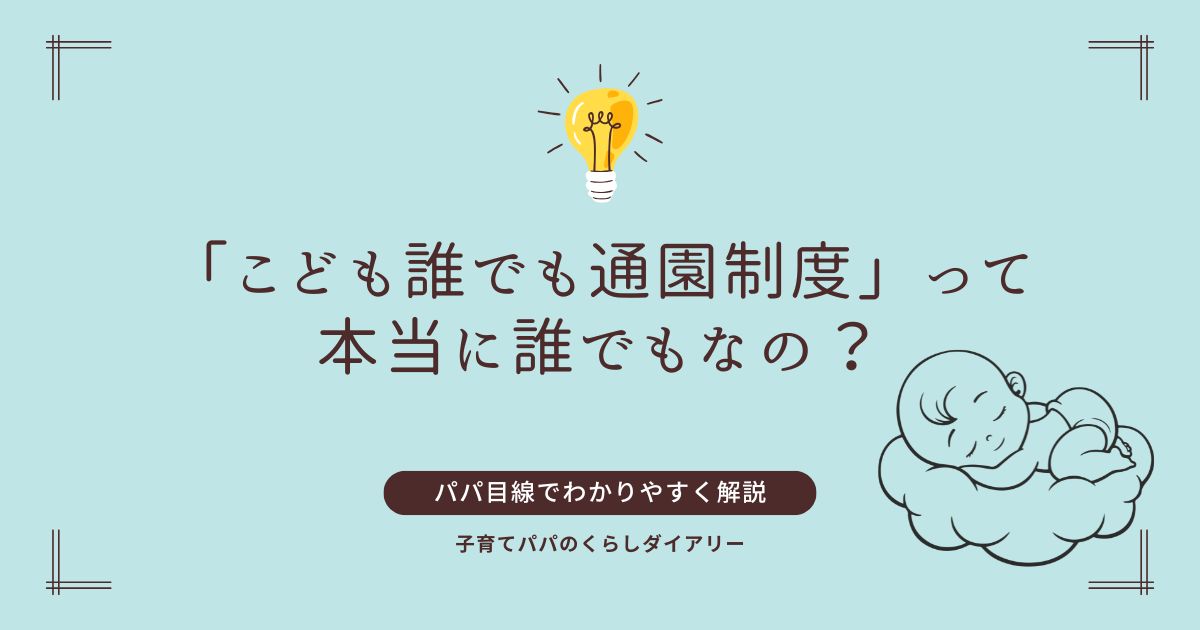

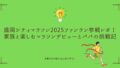
コメント